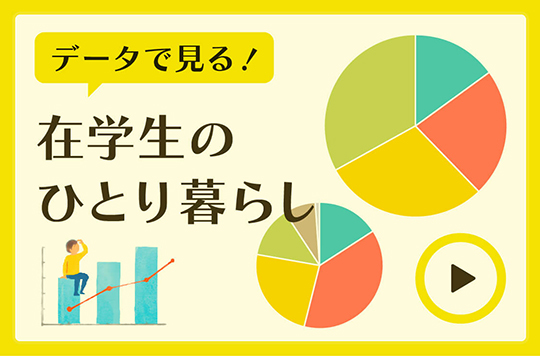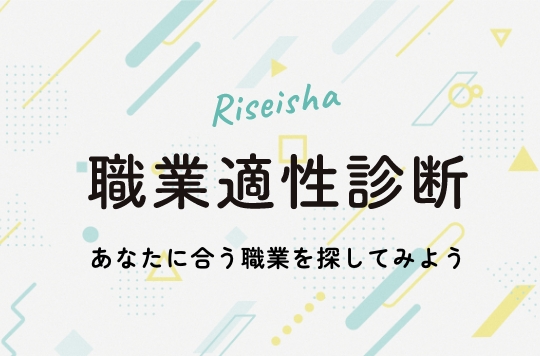年末の風物詩のひとつ、ベートーヴェン作曲の「交響曲第九番」。
「ん?第九って?」という人でもメロディを聴くと「ああ、あの曲か」となるクラシックの名曲です。毎年暮れになると各地で演奏され、特に日本人はこの曲が好きなようです。
この「第九」。日本で初めて演奏されたのは、東京の立派なホールでもなければ、プロオーケストラが演奏したのでもありません。今から102年前、徳島県板東町(現・鳴門市大麻町)にあった板東俘虜(ふりょ)収容所で、演奏したのは第一次世界大戦で敗れたドイツ兵捕虜でした。
日本は第一次世界大戦で連合国側に属し、敵国のドイツ兵捕虜約4500人を、最終的には国内6か所(期間を通して大阪を含む16か所)で収容しました。収容所と聞くと、暗く過酷で非人道的なイメージがありますが、当時、世界から国柄を認めてもらいたい日本は捕虜の扱いに配慮。また、最先端だったドイツ人が持つ技術や文化を習得するという国策もあって、彼らには比較的自由が与えられていました。
中でも「第九」初演の板東俘虜収容所は、模範的な所だったようです。その背景には責任者である松江豊寿所長の考えが大きく影響していました。松江所長は会津藩士の末裔。明治維新の戊辰戦争で敗れ、辛い思いをした人々の中で育ち、負けた者の苦しさを理解していたと言われています。「敵といえども、戦が終われば重んじる」武士道のようなものを感じます。
地元紙である徳島新聞発行の書籍「第九、永遠なり」には「約1000人のドイツ兵捕虜は多彩な文化活動やスポーツに打ち込み、製パンや食肉加工などの技術を地域に伝えた。こうした自由な気風の中、ヘルマン・ハンゼン一等軍楽兵曹が指揮する徳島オーケストラは、1918年6月1日、屈指の難曲であるベートーヴェンの第九に挑み、日本初演という歴史を刻んだ」と記しています。
私が驚いたのは、捕虜と地元の人々が交流していたこと。しかも、収容所のあった板東村の人口は当時5000人余りで、そこにいきなり約1000人ものドイツ人がやって来た。6人に1人がドイツ人の計算になるのです。これ、大正時代の話です。少し前のインバウンドどころではありません。はじめはお互いにいろいろあったと思いますが、当時の日本人は西洋の優れた文化や技術に触れ、学ぶことにワクワクしたことでしょう。「こんなチャンス生かさな損!」と思ったんですかね。「知りたい!」という好奇心や探究心は人を動かし、成長させる原動力になるものです。
音楽についても行動力あふれる若者たちが、バイオリニストの捕虜に演奏を学んだそうです。そのうちの一人は後に徳島市で洋楽器店を営み、音楽教室を開いて地元の文化振興に貢献しました。
また、スポーツでは地元の教員50名が収容所を訪れ、捕虜たちは鉄棒やあん馬の器械体操、重量挙げを披露。その後、捕虜たちが体育指導に近隣の学校へ行くようになったとか。そのうちの一校だった撫養中学(現・鳴門高校)からは偶然にも1988年ソウル、92年バルセロナ五輪の体操男子団体で2人の銅メダリストが誕生しています。直接ではないでしょうが、何かをその地に残したのではないでしょうか。
一方、教えるドイツ人もいくら自由とはいえ、極東の地で捕らわれの身では、望郷の思いが募ったに違いありません。でも「教える」「必要とされている」ことに熱くなったと思います。
戦争が終わり、やがて彼らは釈放されて国に帰っていきましたが、大学で教鞭をとったり、様々な分野で技術指導にあたったりと、各地の収容所にいた捕虜の中から自分の意思で日本に残る人がいました。バームクーヘンで有名な神戸のドイツ菓子店ユーハイムも広島・似島で収容された捕虜のひとりが起こした企業で、今日も続いています。
さらにうれしいことは100年以上たった今でも板東の人々とドイツ人元捕虜、その子孫が交流していることです。1960年代には鳴門市役場に元捕虜からの手紙が届き、収容所跡地を再訪する人もいました。一方、旧板東の人もドイツ兵の慰霊碑を守ってきました。「第九」初演から100年目年の2018年には、記念コンサートが行われ、元捕虜の子孫たちが訪れました。これも奇跡のようなことだと思います。
「第九」で盛り上がる第4楽章のタイトルは「歓喜の歌」。「人類の融和」「全ての人々は兄弟になる」とベートーヴェンは思いを込めています。ドイツ兵捕虜と日本人との交流は、両国の“一般の人々”の「他者を思う」「知りたい、学びたい」「役に立ちたい」といった思いが集まり、人と人がつながって生まれたものだと思います。
今年は新型コロナウィルスなど、まさかのことが起きました。ソーシャルディスタンスは必要ですが、思いやるとか、探究心を持つことで心の距離が縮まれば、乗り越えられるのではないでしょうか。来年は「歓喜の歌」が街中にこだまする、そんな年になってほしいものです。
◇
「歓喜の歌・第九」。この曲を創ったとき、ベートーヴェンの耳はほとんど聴こえていなかったそうです。これも奇跡ですね。